|
|
 |
|
2024年の節分は、2月3日!恵方は「東北東」
|
|
もともと節分は立春、立夏、立秋、立冬の四季の分かれ目を示す言葉で、年4回ありました。その中で冬から春への季節の移り変わりが新しい年を迎える一年の始まりを意味するものとして大切にされ、立春前の節分が暦の言葉として様々な行事と共に残されてきました。
疫病や悪鬼を追い払う追儺(ついな)の行事もかつては大晦日に行われていたようですが、民間の正月行事などと混交し、現在の節分の行事になったと考えられています。 節分には神社仏閣では炒った大豆をまき、家庭でも「鬼は外、福は内」の掛け声とともに豆をまきます。豆をまくのは、そもそもは鬼を追い払うためではなく神仏に対する供物(くもつ)の意味であったと言われています。 また、地域によっては門口に鰯(いわし)の頭と柊(ひいらぎ)の葉を飾る習俗もあります。これは鰯の臭いと柊の棘(とげ)で悪疫をはらう意味があると伝えられています。 節分を境に翌日の立春からその名の通り春が訪れます。暦の雑節で茶摘みや苗代の籾まきの目安とされる「八十八夜」、稲の開花の時期と共に台風が来る時期でもある「二百十日」などはいずれも立春から数えた日にちであり、かつての暮らしの中で節分や立春が重要な意味をもっていたことがわかります。 節分は立春の前日で、ほとんどの年で2月3日がその日に当たります。しかし立春は2月4日に固定されたものではありません。 地球が太陽の周りを1周すると1年ですが、1周にかかる時間は厳密には365日ではなく、365日と約6時間かかります。この差を調節するために閏年がありますが、地球が立春の位置を通過する時間単位で見るとわずかにゆらぎがあるため、立春の日付が前後します。立春の日付が前後することにあわせて、前日の節分も動くことになるのです。 今年の節分は2月3日です。 |
|
|
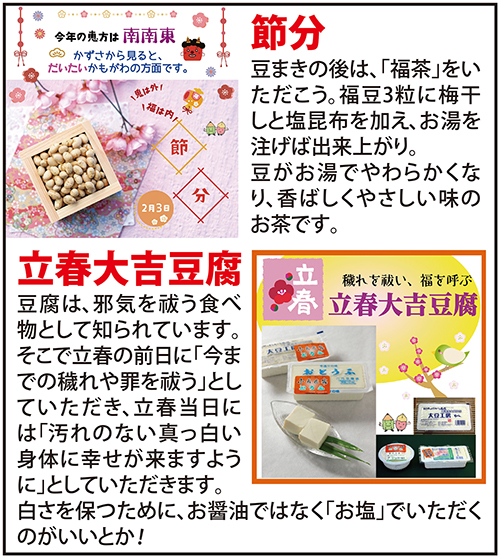
|
|

|
|
| 坂東三十番高倉観音(平野山高蔵寺) | ||||||||||||
 33ヵ所霊場第30番札所として「高倉観音」の名で親しまれています。本尊の正観世音菩薩は約3.6mの高さで樟木一本彫りでは全国札所の中で最大級を誇っています。 |
|
|||||||||||
|
|
| 成田山 新宿不動堂 | ||||||||||||
 当山は、遠く江戸時代までさかのぼり当時は、羅漢寺という寺であった。またその頃より現在同様に、『新宿のお不動様』といわれており随分昔からお不動様との縁が深かったことが、大本山 成田山新勝寺にある仏教図書館の文献や鳥瞰図にも記されている。 |
|
|||||||||||
|
|
| 新御堂寺 | ||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||
|
|
| 鹿野山 神野寺 | ||||||||||||||
 |
|
|||||||||||||
|
|
| 木更津総鎮守 八剱八幡神社 | ||||||||||||||
 当社の社伝によると往昔このあたり一帯の地を八剱の里と呼び、この里の神を八剱の神と称え、この神に仕えるはふりを八剱と申した。 |
|
|||||||||||||
|
|
| 山王山 薬王院 円如寺 | ||||||||||||||
 円如寺は千葉県君津市・久留里にある、真言宗智山派の寺院です。開創は應永2年(西暦1395)と伝えられており、江戸時代には久留里城主黒田公の祈願所でありました。本尊は大日如来。また薬師堂には、病気平癒の仏様・薬師如来もいらっしゃいます。 毎年秋には「萩まつり」が行われ、手入れの行き届いた約500株が咲き乱れる様は、見応え充分です。 上総の七福神「寿老神」も祀られています。 |
|
|||||||||||||
|
|
| 東京湾観音 | ||||||||||||||
 東京湾観音は、東京湾を一望できる南房総国定公園(大坪山)に建つ高さ56mの救世観音です。 本像は昭和36年に宇佐美政衛氏が世界平和の理念の元に建立されました。そのお姿は平和な世の中を祈願した珠を懐き、常に我々の幸せを願う安らかなお顔です。 |
|
|||||||||||||
|
|